見出しまわりの調整
さっそく、見出し部分から調整して行きましょう。 前回、共通で使っている「h2box」クラスの設定はしているので、微調整ですね。
hタグ内の<br>に、d-pc-noneクラスを加えて改行をなくします。
<h2 class="mb-0">
Webデザイナースキルが<br class="d-pc-none">上がる理由
</h2>
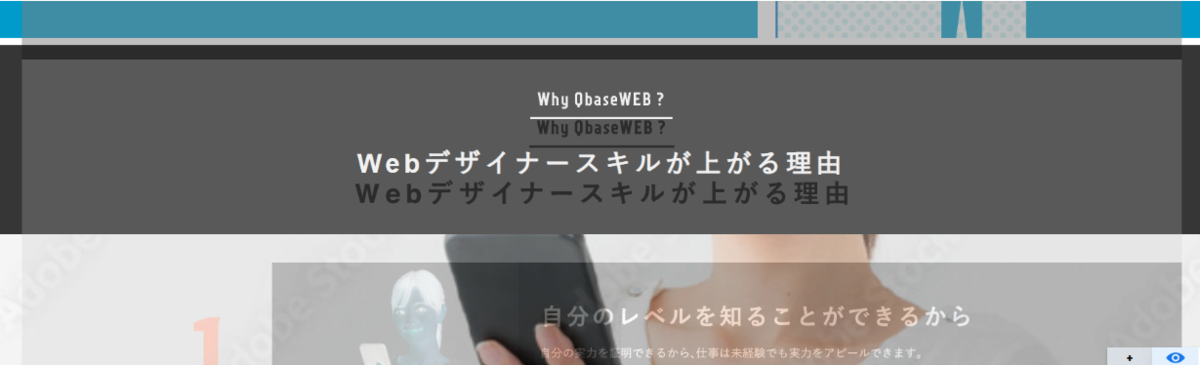
カンプに合わせて、余白を調整します。
/* ---------------------- */
/* Why Qbase Web
/* ---------------------- */
.why{
margin-top: 30px;
}
.why .h2box{
padding-top: 80px;
}
.why .h2box h2{
letter-spacing: 0.18em;
}
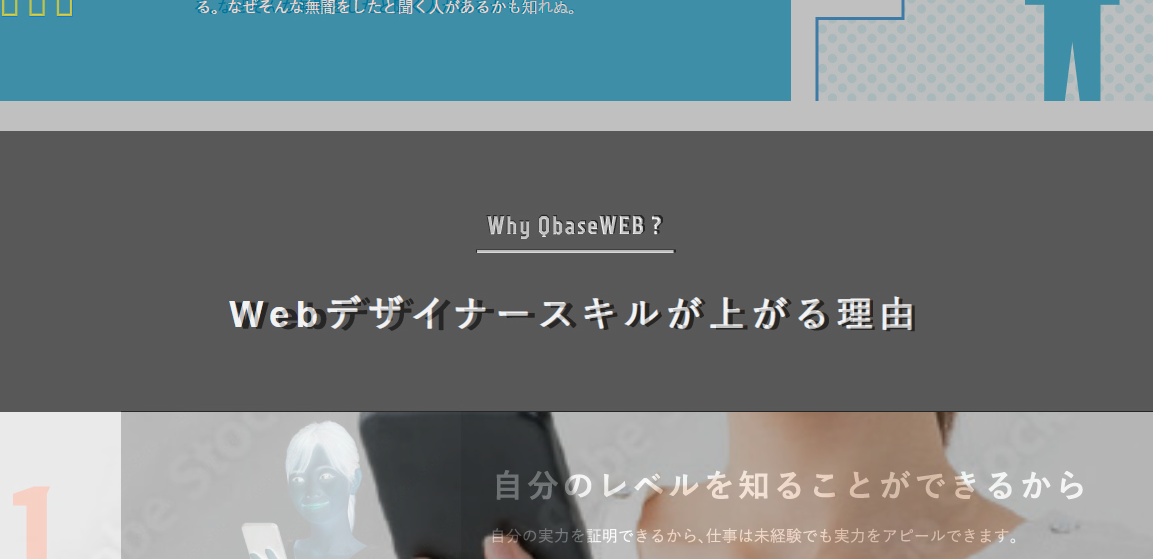
3カラム部分の作成
1.幅と配置を合わせる
理由1~3のブロックを作ります。 写真とテキストを囲んでいるdiv(.why-item_desc)をdisplay:flex;にすると、3つのブロックは横並びになりますね。

ただ、このまま横並びにするだけでは、幅が広がりすぎます。 why-itemクラスをもつdivに「container」クラスを加えます。
<div class="why-item d-flex container px-0">
左右paddingをつけたくないので、「px-0」というクラスも作りました。 CSSファイルで、余白クラスのほうを上に書いていると効きません。 .conteinerよりも下に移動します。
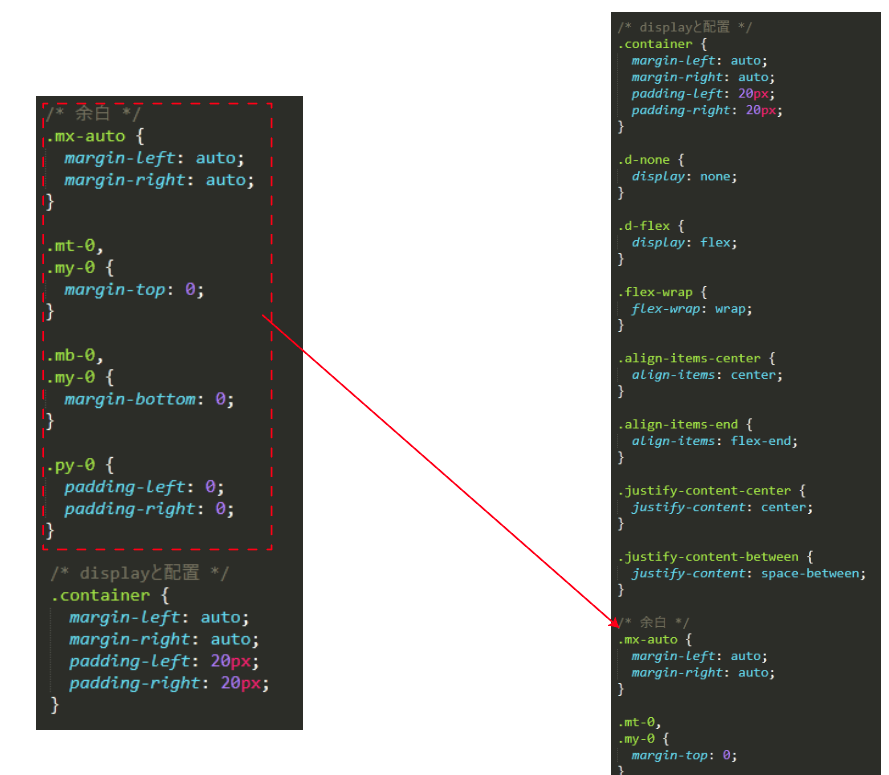
div.why-itemの幅は合いました。

why-item_descクラスのdivに「d-tb-flex」クラスを追加します。
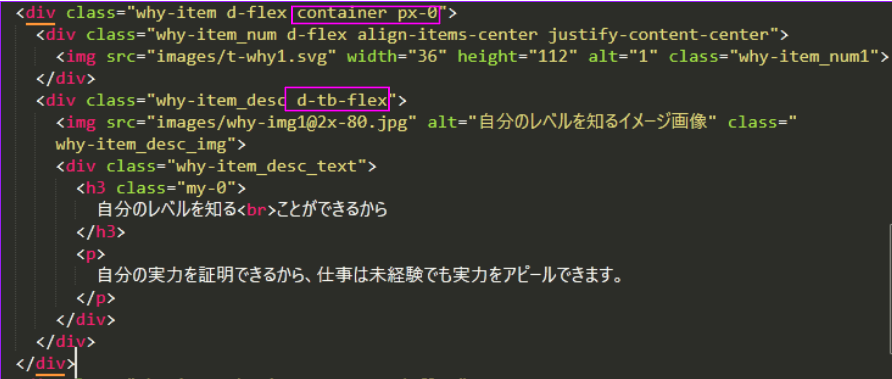
写真部分の幅は広いですが、横並びにはなりました。

2.各要素のサイズを合わせる
それぞれのサイズをカンプに合わせていきます。
.why-item_num {
flex: 0 0 135px;
}
.why-item_desc_img {
max-width: 340px;
height: 270px;
}
.why-item_desc_text{
padding: 50px 30px;
}
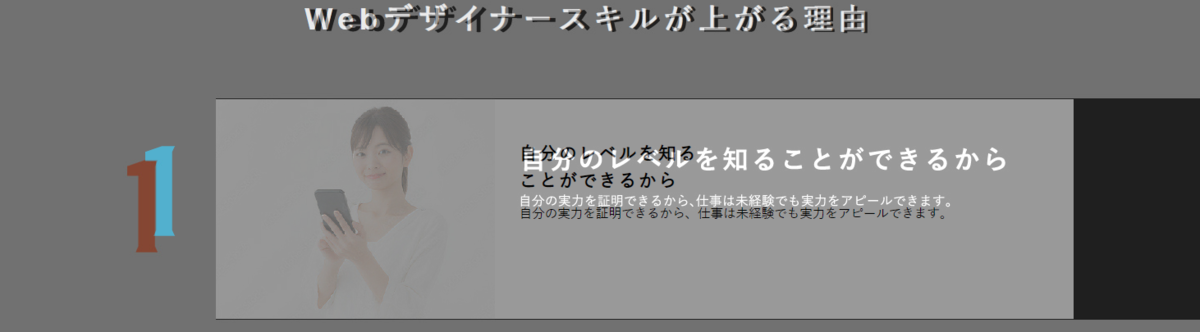
h3タグの中にある<br>を<br class="d-pc-none">にして、改行を無くします。
見出しのフォントサイズも合わせましょう。
.why-item_desc_text h3 {
font-size: 32px;
}
.why-item_desc_text p {
margin-top: 13px;
}
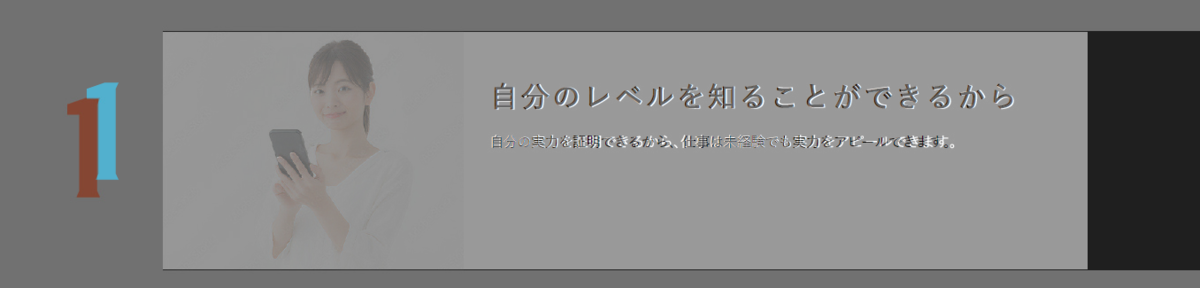
数字の部分のズレを調整します。 検証ツールで見てみると、カンプの数字はleftでもcenterでもない微妙な位置にありますね(薄く見えるオレンジの数字がカンプの位置)。
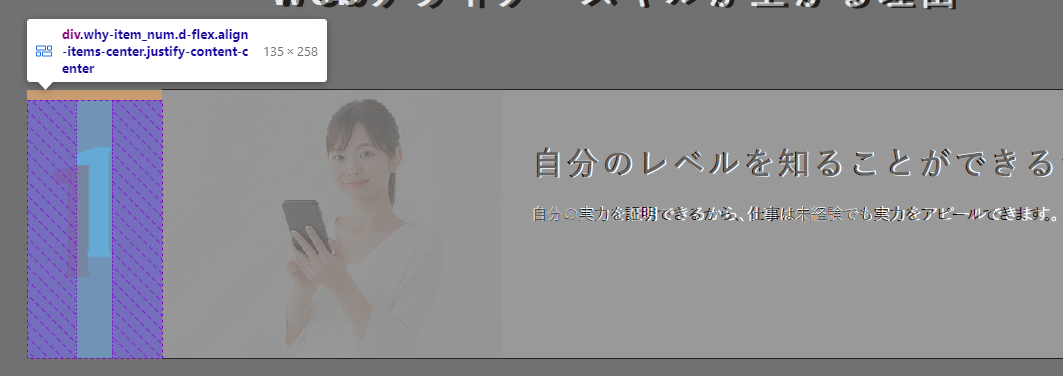
padding-rightを使って、デザインの位置まで押す形にします。
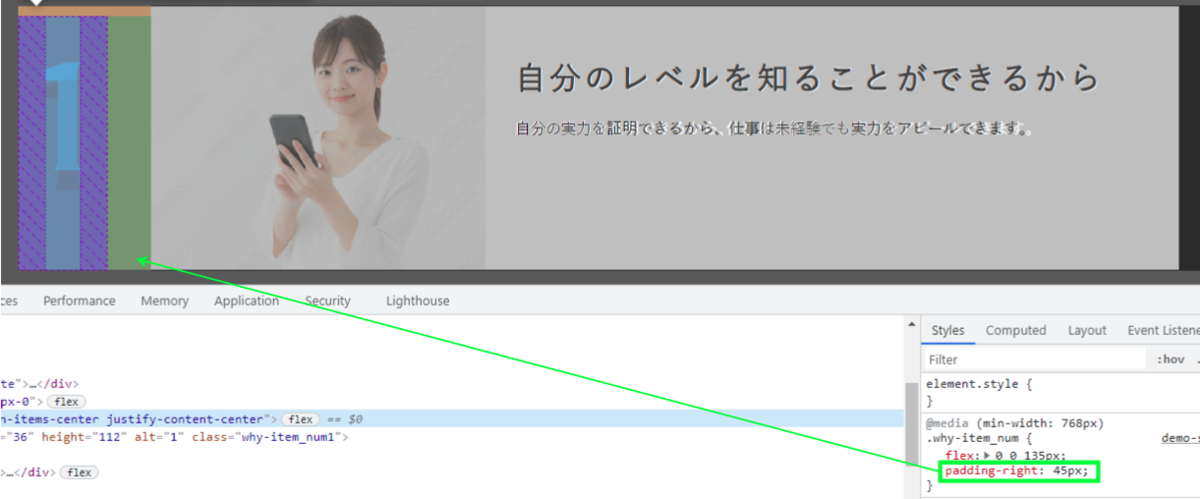
更に、画像(why-item_num1クラス)のmargin-topの値を上書き。 縦方向の位置も揃えます。
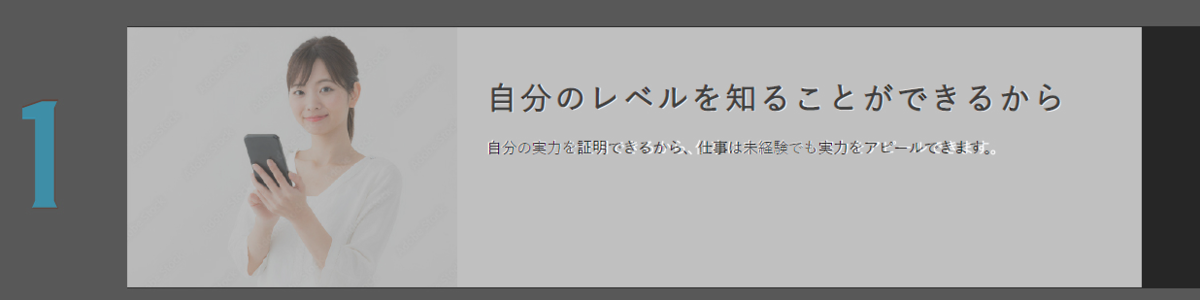
3.白背景を端まで伸ばす
横並びにしたブロックは、幅が広がってもコンテンツはconteiner幅で固定されます。 しかし、テキスト部分+画面端まで白背景は繋がったデザインです。
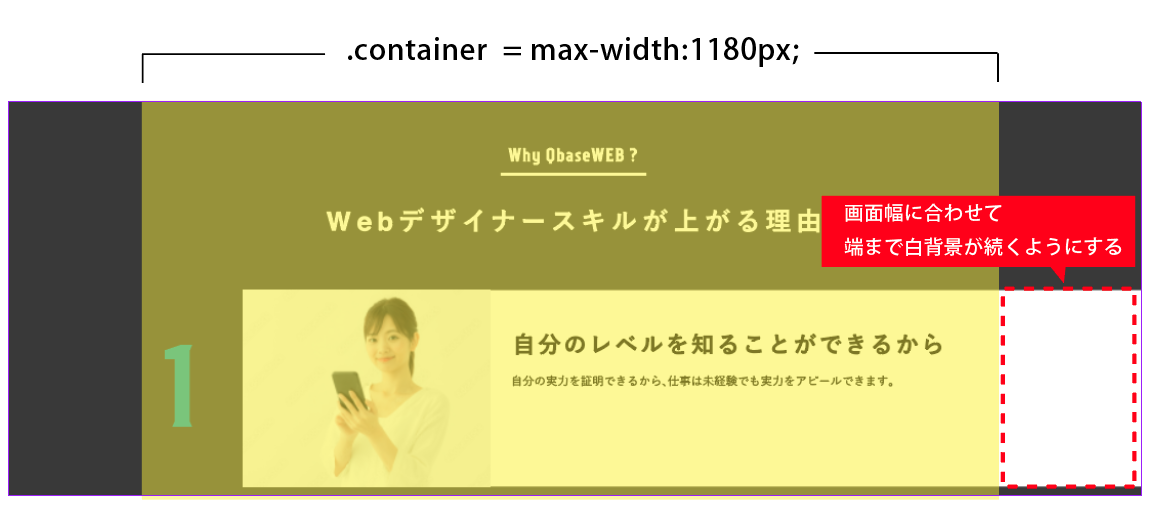
こうした場合、作り方は何通りかあります。 今回はシンプルなデザインで、conteinerは常に画面中央に配置されます。 なので、グラデーションを作る時に使う「background: linear-gradient()」を使って白い部分を作ります。
why-itemを囲うdivの作成
背景を設定するために、why-itemクラスのdivを囲います。 「why-item-bg」というクラス名を付けました。
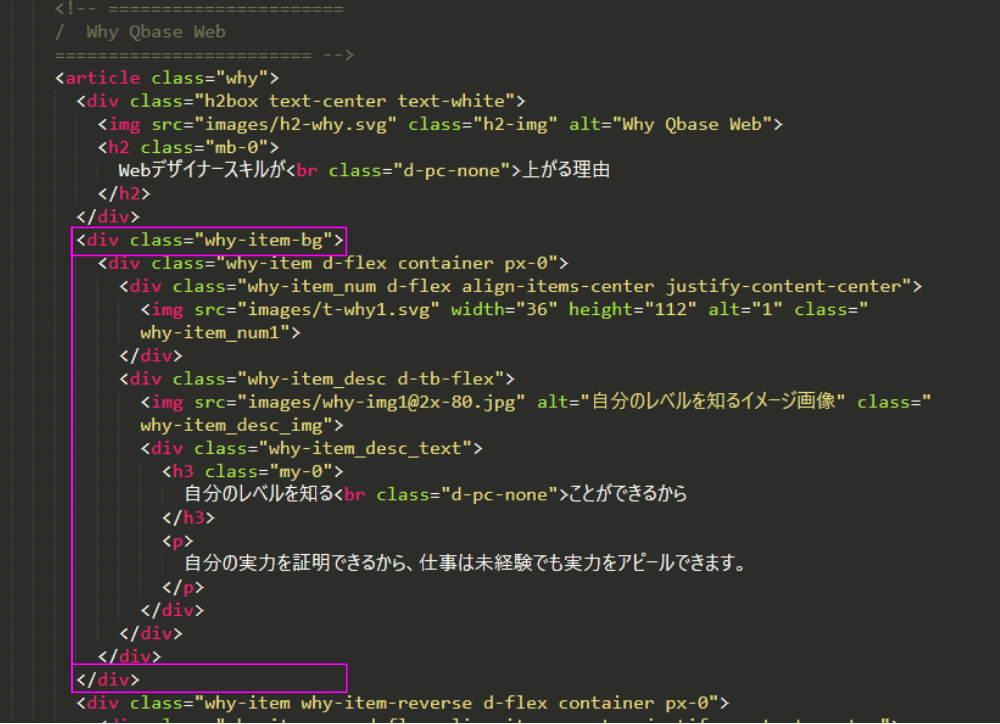
cssで背景を指定する
50%の位置で背景色透明と、背景色白をパッキリと分けます。
.why-item-bg {
background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, transparent 50%, #FFF 50%, #FFF 100%);
}
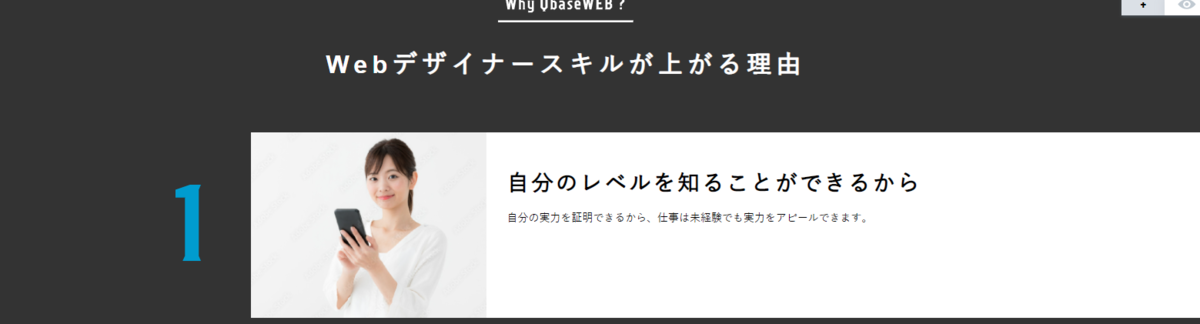
重なっているので分かりにくいですが、背景色は下記のように入っています。
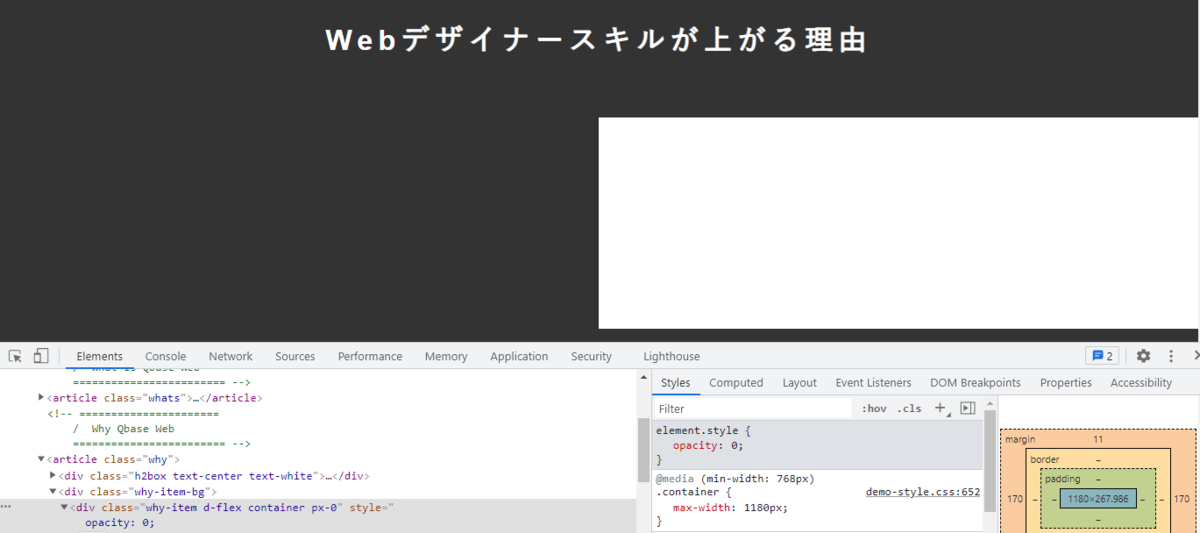
「2」のブロック(逆位置)を作る
2番めは配置順が逆になるので、CSSで合わせましょう。

背景色の配置を逆にするために、「why-item-bg-reverse」クラスを作りました。
<div class="why-item-bg-reverse">
<div class="why-item why-item-reverse d-flex container px-0">
/* 逆位置 */
.why-item-bg-reverse {
background: linear-gradient(90deg, #FFF 0%, #FFF 50%, transparent 50%, transparent 100%);
}
.why-item-reverse .why-item_num {
padding-left: 48px;
padding-right: 0;
}
.why-item-reverse .why-item_desc_img{
order: 2;
}
.why-item-reverse .why-item_desc_text{
order: 1;
width: 630px;
margin-top: 5px;
margin-left: auto;
}
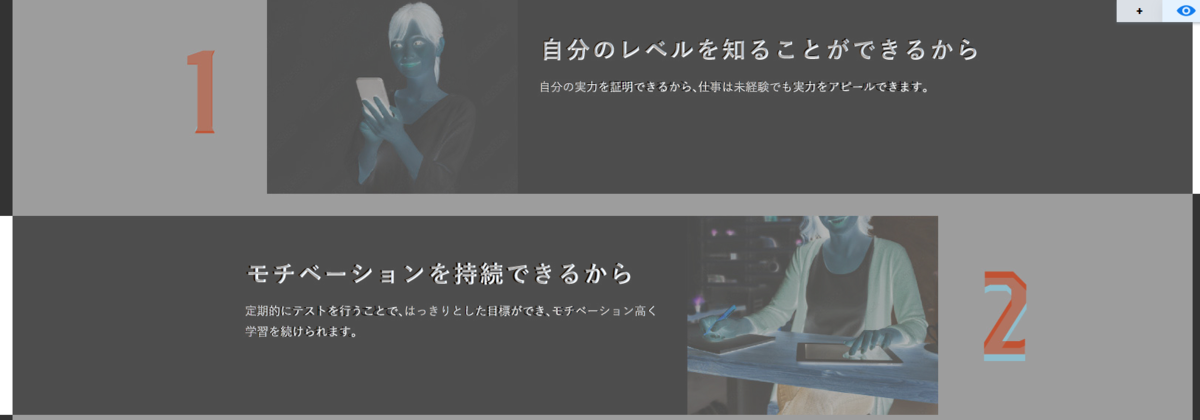
数字の部分は「3」と合わせて調整しましょう。
「3」のブロックを作る
3のブロックは、下に画像が2枚あるので、少し作り方を変える必要があります。
上の段、下の段に該当する部分を、それぞれ<div class="d-tb-flex">で囲いましょう。
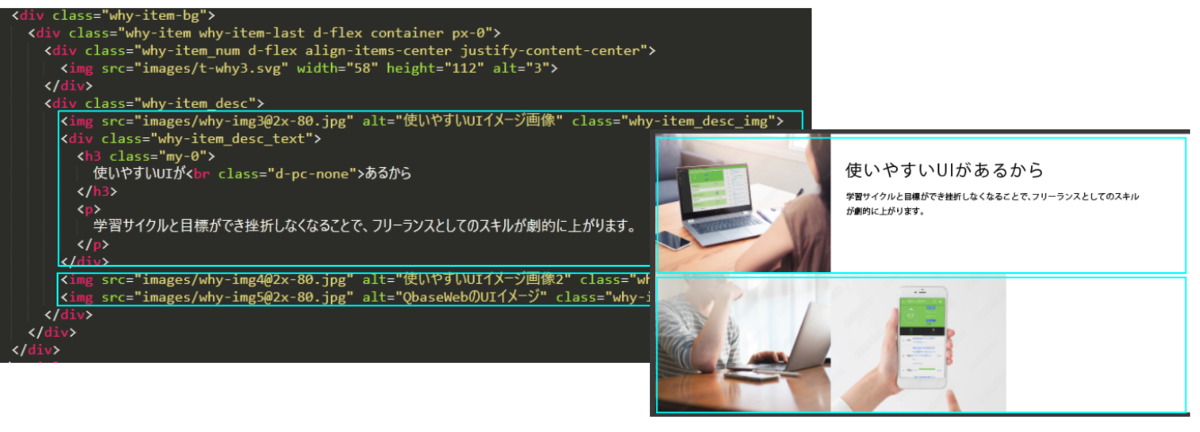
↓
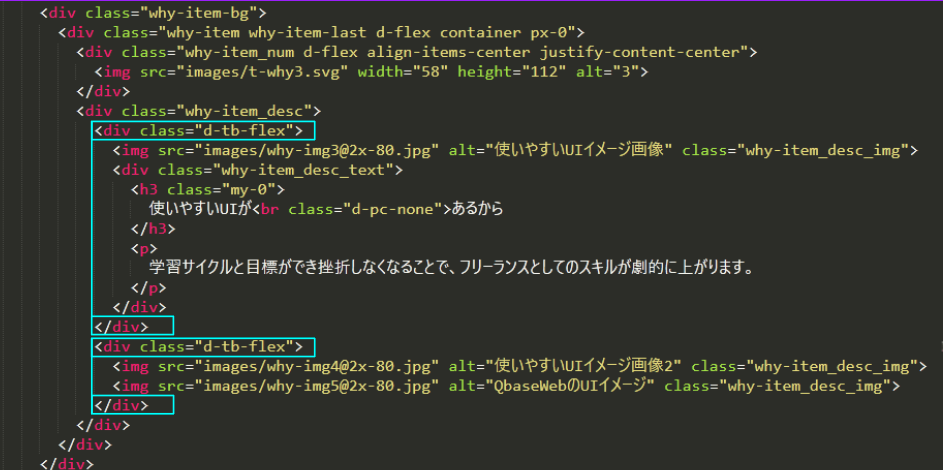
カンプの形になりました。

最後に少しズレているところを、CSSで直せばOKです。

タブレット幅の調整
作った箇所をタブレット幅で見てみましょう。 widthやheightを固定値で書いているので、はみ出しが出てしまっています。

崩れの原因となっているスタイル指定を@media (min-width: 1200px) {}の内に移動させ、調整していきましょう。タブレット幅の方は崩れない値を入れます。
【CSS調整例(一部のみ抜粋)】
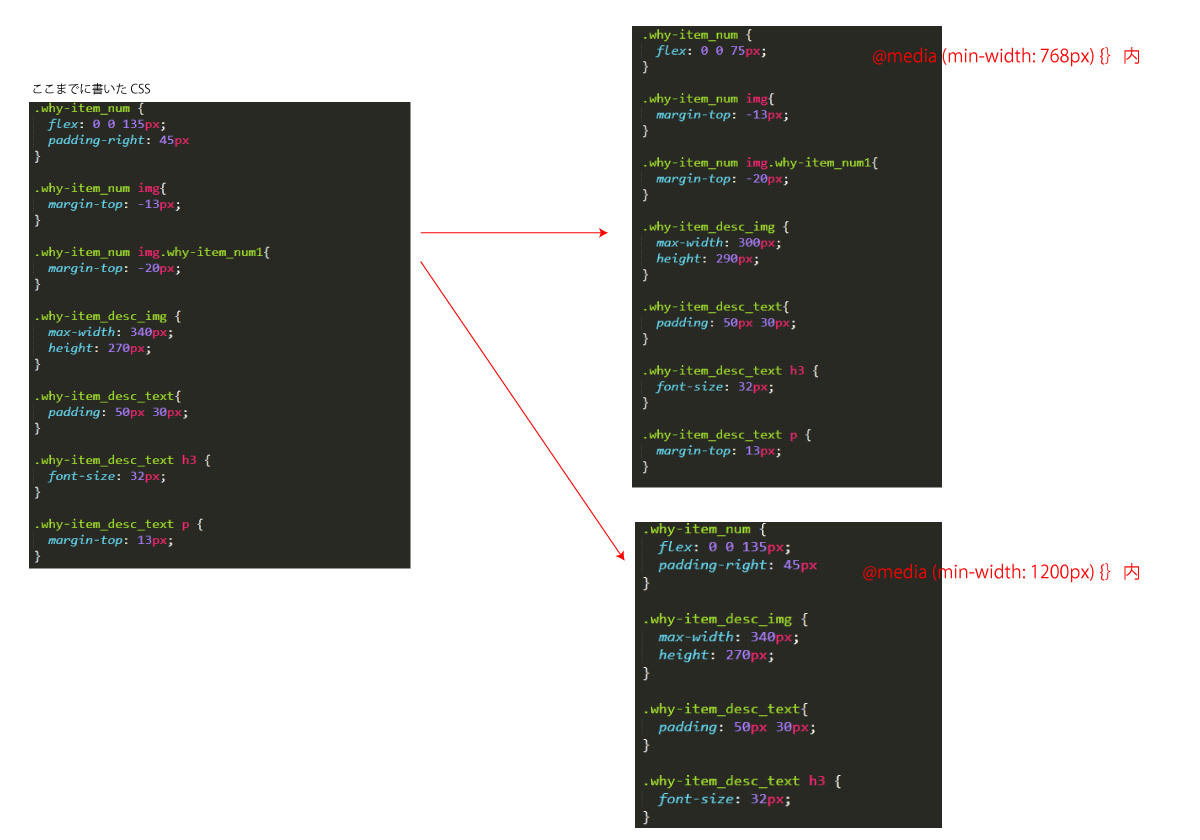

タブレットとのCSS振り分けまでを終えたデモコードは、素材からダウンロードして確認いただけます。
